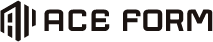BLOG LIST
ブログ一覧
家づくり 2025.11.13
買ってはいけない土地の7つの特徴とは?プロが教える見分け方と後悔しないためのチェックリスト
目次
- 【プロが解説】買ってはいけない土地の7つの特徴と見分け方
- 【結論】買ってはいけない土地の7つの特徴
- 買ってはいけない土地を選んでしまう「3つの理由」
- プロが教える!買ってはいけない土地の「見分け方」3ステップ
- 【深掘り】予算オーバーを防ぐ「総費用」の考え方
- まとめ:後悔しない土地選びは信頼できるパートナー探しから
【プロが解説】買ってはいけない土地の7つの特徴と見分け方
「家づくりは、土地探しから」と言われますが、理想のマイホーム計画が土地選び一つで台無しになってしまうケースは少なくありません。「価格が安いから」と安易に決めてしまい、後から「家が建てられない土地だった」「地盤改良に数百万円の追加費用がかかった」と後悔する声は後を絶たないのです。
特に、ハウスメーカーで予算が合わず、土地代を抑えようと考えている方は注意が必要です。その「掘り出し物」に見える土地、本当に大丈夫でしょうか?
今回は、兵庫県姫路市・たつの市エリアで、一級建築士とつくるデザイン性と性能を両立した家づくりを手がけるACE FORMが、プロの視点で「買ってはいけない土地」の7つの特徴を徹底解説します。
この記事を読めば、以下の点が明確になります。
・絶対に避けるべき土地の7つの特徴
・なぜ危険な土地を選んでしまうのか?
・プロが実践する「危険な土地」の見分け方(資料・役所・現地調査)
・予算オーバーを防ぐ「総費用」の正しい考え方
土地探しで失敗しない知識を身につけ、安全に、そして賢く理想の家づくりを進めるための一歩として、ぜひ最後までご覧ください。
【結論】買ってはいけない土地の7つの特徴
土地探しで後悔しないために、購入を避けるべき土地には共通の特徴があります。高額な買い物で失敗しないよう、契約前に確認すべき7つのポイントを詳しく解説します。
1. 災害リスクが高い(ハザードマップで要確認)
まず避けるべきなのは、洪水、土砂災害、津波といった災害リスクが高い土地です。安全な生活の基盤となる土地が、災害に脆弱であってはなりません。
具体的には、国や自治体が公開している「ハザードマップ」で、浸水想定区域や土砂災害警戒区域(イエローゾーン・レッドゾーン)に指定されている土地です。川の近くや海抜の低い土地、崖や山の麓などは、価格が安くても相応のリスクを抱えています。
購入を検討する際は、必ず「ハザードマップポータルサイト」などで、その土地の危険度を自分の目で確認してください。リスクを許容できるか、厳しく判断することが重要です。
2. 地盤が弱い(地盤改良に高額費用も)
地盤が弱い土地も注意が必要です。家が傾く「不同沈下」のリスクがあるほか、最悪の場合、高額な地盤改良工事が必要になるためです。
特に、以前が田んぼ、沼地、埋立地だったエリアは、軟弱地盤の可能性があります。地盤の強さは見た目では判断できず、建築前の地盤調査で初めて判明します。地盤調査の結果、軟弱地盤と判明した場合、工法によりますが一般的に80万~250万円程度の地盤改良費が追加で発生します。特に地盤が悪い場合や敷地が広い場合、数百万円に達するケースもあります。
契約前に地盤調査データがないか確認する、「沼」「沢」「谷」など水に関連する旧地名が残っていないか調べる、といった対策を取りましょう。

3. 形状が悪い(旗竿地・極端な変形地・間口が狭い)
土地の形状が悪い(不整形地)と、希望の間取りが実現できなかったり、建築費用が割高になったりする「リスク」があります。
例えば、道路からの通路が細長い「旗竿地」は重機が入りにくく、建築費が上がりがちです。三角形やL字型といった「極端な変形地」はデッドスペースが生まれやすいのも事実です。
しかし、相場より安価なこれらの土地は、設計力次第で「掘り出し物」に変わる可能性を秘めています。ハウスメーカーの規格住宅では対応が難しくても、一級建築士のいる工務店であれば、土地の個性を活かしたユニークな間取りを実現できるケースも少なくありません。
その土地に本当に希望の建物が建つか、どれくらいの費用でデメリットをカバーできるか、早い段階で専門家に相談することが重要です。
4. 道路との高低差が大きい・古い擁壁がある
道路や隣地との高低差が大きい土地は、追加の造成費用や「擁壁(ようへき)」の管理リスクを伴います。
高低差があると、階段やスロープが必要になったり、駐車スペースの確保が難しくなったりします。特に注意すべきは擁壁です。ひび割れや傾きがある古い擁壁は、安全基準を満たしておらず、作り直し(再築造)が必要になる場合があります。擁壁工事は非常に高額になるため、深刻な隠れコストと言えます。
高低差のある土地は、擁壁の状態を目視で確認し、必要であれば専門家の診断も検討しましょう。
5. インフラ(上下水道・ガス)が未整備
生活に必須のインフラ、特に上下水道が敷地内に整備されていない土地は注意が必要です。引込工事に高額な費用が別途発生するためです。上水道の引込工事だけで30万~50万円程度が相場です。さらに下水道が未整備のエリアでは、浄化槽の設置費として80万~120万円程度が加わります。合計で150万円以上の初期費用がかかる可能性も考慮すべきなのです。
下水道が未整備のエリアでは、浄化槽の設置費と定期的な維持費もかかります。また、都市ガスがなくプロパンガスのみの場合、月々のガス代が割高になる傾向があります。
インフラが「宅内引込済」なのか、単に「前面道路まで」なのか、不動産会社に詳細を確認しましょう。

6. 周辺環境に問題がある(騒音・悪臭・嫌悪施設)
快適な生活を送る上で、周辺環境の問題も見過ごせません。騒音、悪臭、人によっては避けたい「嫌悪施設」が近くにないか確認しましょう。
高速道路や線路の騒音、飲食店の排気やゴミ処理場の悪臭、墓地や鉄塔といった嫌悪施設などは、生活の質(QOL)に直結します。これらは書類上では分からず、現地確認が不可欠です。
必ず、平日の昼間、夜間、そして休日の3つの異なる時間帯に現地を訪れ、自分の目や耳、鼻で「ここで快適に暮らせるか」を確認してください。
7. 隠れたコストが発生する(私道負担・埋設物など)
土地には、見た目では分からない「隠れたコスト」が潜んでいることがあります。代表例が「私道負担」と「地中埋設物」です。
「私道負担」があると、その部分の固定資産税や将来の舗装費用を負担しなければならない場合があります。「地中埋設物」は、過去の建物の基礎やコンクリートガラが地中に残っているケースで、撤去費用は買主負担となることが多いです。
売買契約書の特約事項(特に「瑕疵(かし)担保責任」や「埋設物」に関する記載)を熟読し、不明点をクリアにしてから契約に臨みましょう。
買ってはいけない土地を選んでしまう「3つの理由」
「買ってはいけない土地」の特徴を知った上で、「では、なぜ多くの人がそうした土地を選んで失敗してしまうのか?」という疑問が浮かんでくるのは当然のことです。その原因は、土地の知識不足だけでなく、人間の心理的な「クセ」にもあるのです。

1. 「掘り出し物」という価格の安さだけで判断してしまう
失敗する最も大きな原因は、相場より極端に安い価格に「掘り出し物だ」と飛びついてしまうことです。
不動産市場において、理由なく安い物件は存在しません。「早くしないと他の人に取られてしまう」という焦りから、価格の安さだけで判断を下してしまうのが典型的な失敗パターンです。
しかし、その安さの裏には「再建築不可」「地盤改良に高額な費用がかかる」「古い擁壁の作り直しが必要」といった、後から必ず問題になる理由が隠れています。
例えば、相場より安い「旗竿地(はたざおち)」は、見た目以上に建築時の重機搬入が難しく、建築費が割高になるケースが多いのです。
安い価格は「魅力」ではなく、「なぜ安いのか?」を問う「警告」だと捉えましょう。その理由を徹底的に調査し、納得できる明確な答えが出るまで、安易に契約してはいけません。
2. 情報収集や現地調査の不足(”大丈夫だろう”という思い込み)
「プロの不動産会社が紹介するんだから大丈夫だろう」という思い込みや、面倒くささから情報収集・現地調査を怠ることも、失敗の大きな原因です。
ハザードマップの確認を怠り、水害リスクを知らないまま契約してしまう。あるいは、晴れた日の昼間1回だけ現地を見て「日当たり良好」と判断してしまう。これらは非常に危険です。土地の本当の姿は、時間帯や天候によって一変します。
・平日の朝夕の通勤ラッシュ時の交通量や騒音
・夜間の街灯の少なさや、周囲の静けさ(または騒がしさ)
・雨の日の水はけの状態
こうした「住んでから気づく問題」は、書類上ではわからず、自分の足で時間帯や曜日を変えて何度も確認する以外に防ぐ方法はありません。「だろう」運転ならぬ「だろう」判断は禁物です。
3. 不動産会社や売主の情報を鵜呑みにしてしまう
不動産会社の担当者や売主の「良い情報」だけを信じ込み、自分で「裏付け(エビデンス)」を取らないこともリスクを見落とす原因になります。
もちろん、不動産会社は売買のプロですが、同時に「売りたい」という立場でもあります。メリットは強調しても、デメリット(例:近くに嫌悪施設がある、冬場の日当たりが悪いなど)は、重要事項説明で軽く触れる程度かもしれません。
「日当たり良好ですよ」と言われたら、それが冬場も本当か、南側に将来高い建物が建つ計画はないかを自分で調べる。「静かな環境です」と言われたら、平日の早朝や夜間にも足を運んでみる。こうした「確認作業」が重要です。
担当者の言葉を疑う必要はありませんが、鵜呑みにせず「自己責任」で最終確認する姿勢が、高額な買い物での失敗を避ける最大のコツです。
プロが教える!買ってはいけない土地の「見分け方」3ステップ
買ってはいけない土地の「特徴」や「失敗する理由」がわかっても、「では、どうやってそれを見分ければいいのか?」が一番知りたいことですよね。
ここでは、不動産のプロが実際に行っている「土地の調べ方」を、3つのステップに分けて具体的に解説します。この手順を踏めば、危険な土地をつかむリスクを劇的に減らせます。

ステップ1:公的な資料で「履歴」と「制限」を確認する
まずは現地に行く前に、パソコンやスマホで「公的な資料」を調べ、その土地の履歴書と法的な制限をチェックします。ここで危険信号が出れば、深追いする必要はありません。
1. 登記簿(登記事項証明書)で権利関係と地目を確認する
登記簿は、その土地の「所有者」や「過去の履歴」がわかる公式な証明書です。法務局の「登記情報提供サービス」などで誰でも確認できます。
権利関係: 所有者以外の権利(例:差し押さえ、抵当権)が複雑に設定されていないか確認します。
地目: 土地の用途を示します。家を建てるには「宅地」である必要があります。「畑」「雑種地」などの場合は、宅地に変更可能か(農地転用など)の確認が必須です。
2. ハザードマップで災害リスクを”再”確認する
これは必須で確認すべきところです。自治体や「ハザードマップポータルサイト」で、洪水、土砂災害、津波などのリスクがどの程度あるのか、色分けされたマップで直感的に確認しましょう。
3. 土地総合情報システムで「相場」を把握する
先ほども触れた「安すぎる土地」の罠にはまらないため、まずは適正価格を知ることが重要です。国土交通省の「土地総合情報システム」では、実際に取引された近隣の土地価格(成約価格)を調べられます。
検討中の土地が、この相場からかけ離れて安い場合は、必ず裏に理由があると疑ってください。
ステップ2:役所で「建てられる家」のルールを確認する
次に、その土地に「そもそも家が建てられるのか?」「どんな家が建てられるのか?」という最も重要なルールを、管轄の自治体(市役所や区役所)で確認します。
訪問すべき窓口は、主に「都市計画課」や「建築指導課」ですが、家づくりの経験がない方がいきなり訪問しても、専門用語が多く、本当に重要な情報を引き出すのは困難です。
1. 都市計画法:家を建てて良いエリアか?
まず確認すべきは「用途地域」です。特に危険なのが「市街化調整区域」に指定されている土地。ここは原則として市街化を抑制するエリアであり、一般の人が住宅を建てることは非常に困難です(再建築不可の可能性大)。
2. 建築基準法:希望の家が建つか?
法律で定められた家の「建て方」のルールも確認します。
接道義務: 敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していないと家は建てられません(再建築不可)。
建ぺい率・容積率: その土地の広さに対して、どれくらいの大きさの家(建築面積や延床面積)を建てて良いかの上限です。これが小さいと、希望の間取りが入らない可能性があります。
これらの情報は、不動産会社が用意する「物件概要書」にも書かれていますが、その情報が最新か、法改正に対応しているか、また「書かれていない情報(例:将来の計画道路)」がないかまで読み解くには専門知識が必要です。
土地の契約前に、こうした法的な確認を建築のプロ(工務店や建築士)に依頼することが、最も確実なリスク回避策です。

ステップ3:現地調査(時間帯・天候を変えて最低2回は訪問)
書類と役所で「問題なし」と判断できたら、いよいよ現地調査です。ここで重要なのは「時間帯と天候を変えて、最低2回は行くこと」です。晴れた日の昼間だけでは、土地の本当の姿は見えません。
1. 五感での確認(騒音・臭い・日当たり)
自分の五感をフル活用し、「生活の快適性」をチェックします。
聴覚(騒音): 平日の朝夕の交通量、電車の音、近隣の工場の稼働音、学校のチャイムや子供の声(許容範囲か)。
嗅覚(臭い): 飲食店の排気、近隣の工場や畜舎、川や用水路の臭い。
視覚(日当たり): 特に「冬の午前中」の日当たりを確認します。南側の建物がどれだけ影を作るかは重要です。
2. 目視での確認(物理的なリスク)
危険な土地の特徴が現地にないか、目で見て確認します。
境界杭: 隣地との境界を示す杭が、すべて設置されているか。
擁壁の状態: 高低差がある場合、擁壁にひび割れ、傾き、水抜き穴からの土砂流出がないか。
周辺施設: 電柱や電線(窓の正面に来ないか)、ゴミ捨て場の位置(清潔に管理されているか)。
3. 近隣住民へのヒアリング(可能な場合)
これは難易度が高いですが、もし近所で作業をしている人や、庭先にいる住民の方がいれば、「この辺りの住み心地はいかがですか?」と軽く尋ねてみるのも有効です。大雨の日の状況や、地域の雰囲気など、住んでいる人にしか分からない貴重な情報が得られることがあります。
【深掘り】予算オーバーを防ぐ「総費用」の考え方
「1,000万円の土地」を買うのに、1,000万円だけ用意しても絶対に家は建ちません。土地購入で失敗する人の多くは、土地の「本体価格」だけを見て予算を組み、後から発生する「諸費用」や「追加工事費」によって、建物本体の予算を削ったり、住宅ローンが膨らんだりする事態に陥ります。
ここでは、予算オーバーを防ぐ「総費用」の正しい考え方を解説します。

土地代金以外にかかる諸費用一覧(仲介手数料、登記費用、地盤改良費など)
土地購入には、物件価格とは別に「諸費用」がかかります。これらは現金での支払いを求められることも多いため、あらかじめ予算に組み込んでおく必要があります。
1. 必ずかかる諸費用(目安:土地価格の5%~10%)
以下の費用は、土地のコンディションに関わらず、ほぼ必ず発生します。
仲介手数料: 不動産会社に支払う成功報酬です。(例:売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税)
登記費用: 土地の所有権を法的に登録(所有権移転登記)するための費用です。司法書士への報酬と、登録免許税(税金)が含まれます。
印紙税: 売買契約書に貼る印紙代です。
ローン関連費用: 土地購入にローン(つなぎ融資など)を利用する場合、金融機関に支払う事務手数料や保証料です。
2. 土地によって発生する「隠れコスト」
ここが予算オーバーの最大の原因です。本記事内で先ほど解説した「買ってはいけない土地」の特徴と直結します。
地盤改良費: 地盤調査の結果、地盤が弱いと判断された場合にかかります。工法によりますが、50万~200万円、あるいはそれ以上の費用が追加で発生します。
インフラ引込費用: 敷地内に上下水道管やガス管が引き込まれていない場合、前面道路から敷設する工事費(数十万~)が必要です。
造成費・擁壁工事費: 土地に高低差がある、または古い擁壁の作り直しが必要な場合、数百万円単位の費用がかかることもあります。
古家解体費: 「古家付き土地」の場合、建物の解体費用(木造で坪4~5万円程度)がかかります。
不動産取得税: 土地を取得した後(数ヶ月後)に、都道府県から請求される税金です。ただし、住宅を新築する場合、要件(床面積50~240平米など)を満たせば、土地・建物ともに大幅な軽減措置が適用されます。この結果、納付額がゼロまたは数万円程度になるケースがほとんどです。申請が必須なため、手続きを忘れないよう注意すべき『コスト』です。
これらの「隠れコスト」を考慮せず、土地代金と仲介手数料だけで予算を組むと、計画が根本から崩れてしまいます。

2. ライフプランから逆算する無理のない土地予算の組み方
では、無理のない土地予算はどう組むべきか。正解は「土地にいくら使えるか」から考えるのではなく、「総予算から、建物代と諸費用を引いた残りが土地予算」と逆算することです。
ステップ1:総予算(借入可能額)を把握する
まずは、あなたの世帯年収や貯蓄、将来のライフプラン(子供の教育費、老後資金)から、「土地+建物+諸費用」の総額でいくらまでなら無理なく返済できるかを把握します。この際、住宅金融支援機構の「住宅ローンシミュレーション」などを活用し、「毎月いくら返せるか」から総借入額を算出するのが安全です。
ステップ2:建物と諸費用の予算を「先取り」する
次に、総予算から「こだわりたい建物の費用」と「諸費用(5-1参照)」を先に引きます。
<予算逆算の例>
シミュレーションの結果、総予算(安全な借入額+自己資金)が4,500万円と判明。
建てたい家のイメージ(希望の広さ・性能)を工務店やハウスメーカーに伝え、概算の建物本体・諸費用で2,800万円かかると試算。
土地の諸費用や地盤改良予備費として、安全を見て200万円を確保。
4,500万円(総予算) – 2,800万円(建物+諸費用) – 200万円(土地諸費用・予備費) = 1,500万円
この「1,500万円」が、あなたが土地の「本体価格」に使える上限予算となります。
多くの人が、先に2,000万円の良い土地を見つけて契約してしまい、残りの2,500万円で家を建てようとして「建物が希望より小さくなった」「キッチンのグレードを落とさざるを得ない」と後悔します。
土地探しは、必ず「総予算」と「建物にかかる費用」を確定させてから始める。これが鉄則です。
まとめ:後悔しない土地選びは信頼できるパートナー探しから
本記事では、「買ってはいけない土地」の7つの特徴から、プロが実践する見分け方、そして予算オーバーを防ぐ総費用の考え方までを網羅的に解説しました。高額な買い物で後悔しないために、これらの知識は必須の「防御策」となります。
しかし、ハザードマップや法律上の制限はご自身で確認できても、「この土地の地盤は本当に大丈夫か?」「古い擁壁の強度は?」「この変形地で希望の間取りが実現できるのか?」といった専門的な判断は非常に困難です。特に、ハウスメーカーで予算が合わず土地代を抑えたい場合ほど、こうしたリスクのある土地に出会う可能性は高まります。
土地の「隠れたリスク」を見抜き、逆に「一見デメリットに見える土地(旗竿地や変形地)を最大限活かす」提案こそが、地域密着の工務店の腕の見せ所です。

私たちACE FORMは、姫路市・たつの市でデザイン性の高い注文住宅を数多く手がけてきた工務店です。在籍する一級建築士や建築免許を持つスタッフが、土地探しの段階から専門家の視点で同行・アドバイスを行います。「ハウスメーカーでは予算が合わなかった」という方もご安心ください。ACE FORMは、月々の返済負担を抑えたい若い世代の方に向けた「50年住宅ローン」の取り扱いなど、資金計画のご相談にも強みがあります。
「この変形地、どう思う?」「この土地で総額いくらになる?」といった具体的なご相談からでも構いません。姫路市・たつの市で土地探しに少しでも不安があれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

▼注文住宅のデザインが知れる「無料のコンセプトブック」を配布中です!
【この記事の監修者】
ACE FORM代表 堀岡慶輔 / 一級建築士

一級建築士として建築業界に長年従事。ハウスメーカーでの経験を活かし、顧客の暮らしを第一に考えた住宅提案を行うACE FROMの代表を務めています。
株式会社ACE FROMの代表として、革新的な建築デザインと顧客満足度を追求。
一級建築士としての豊富な経験と専門知識で、高品質な住まいづくりを提供いたします。